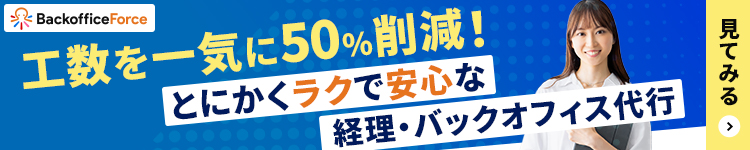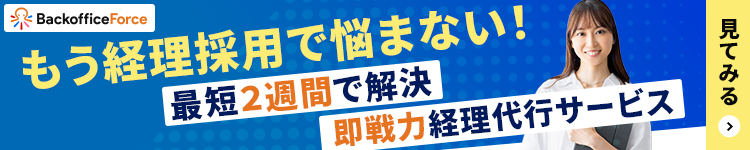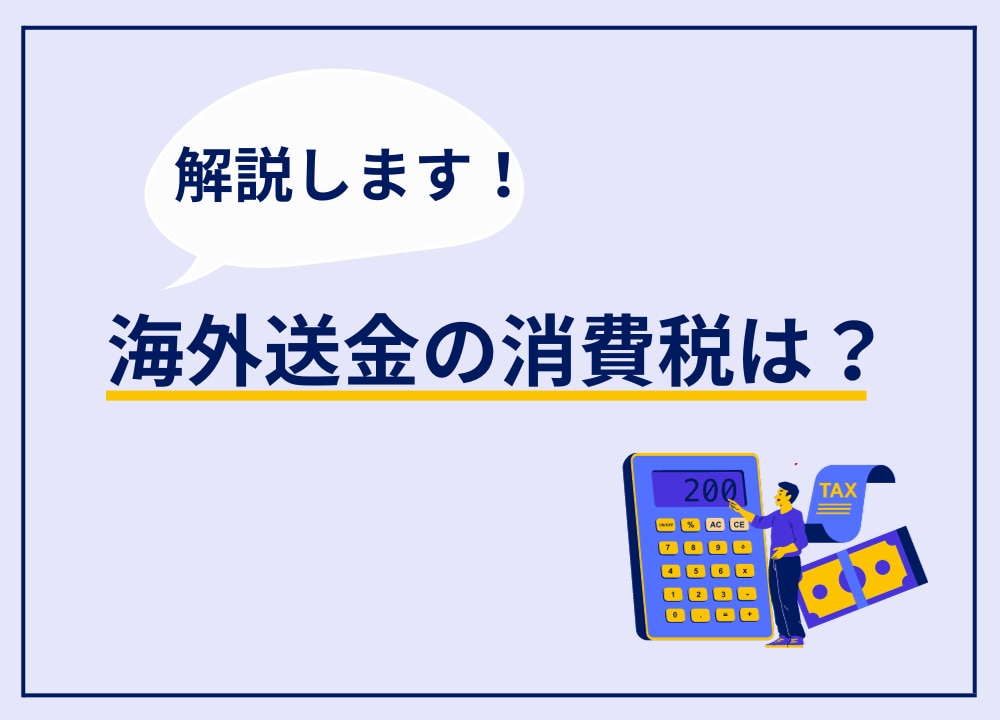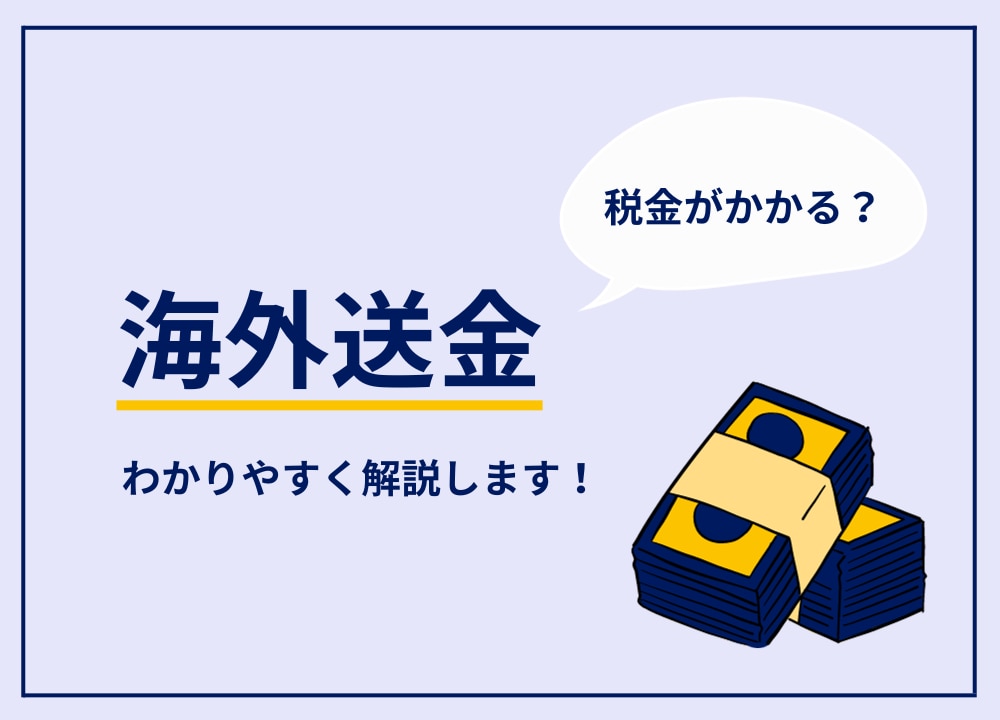経理業務の属人化を解消する方法とは?原因やリスクなど詳しく解説

経理業務を特定の従業員だけが把握している状態になっていないでしょうか。属人化を放置すると、業務停滞や情報漏えいなど、思わぬリスクを招きかねません。
本記事では、経理業務が属人化する背景や、放置することで生じるリスク、さらに解消するための具体的な対策やメリットを詳しく解説します。経理体制の見直しを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
経理業務の属人化とは

経理業務の属人化とは、仕訳や決算作業、税務対応などの専門的な経理業務やノウハウが、一部の担当者のみに集中している状態を指します。
例えば、特定の社員しか使えない会計ソフトがある、請求書発行や振込処理を一人だけが担当している、業務の流れが口頭伝承で引き継がれているなどが具体例です。
こうした状況が続くと、その担当者が不在になった際に業務が滞ったり、他の社員が手を出せずトラブルが拡大する恐れがあります。経理体制の安定には属人化の解消が欠かせません。
なぜ経理業務は属人化しやすいのか?
経理業務は、専門知識を要するうえに細かい作業が多いため、属人化しやすい特徴があります。背景には以下のような要因があります。
- 業務量に対して人手が不足している
- ベテラン社員に知識が集中している
- 経理業務がマニュアル化されていない
次項では、それぞれの要因を詳しく解説します。
業務量に対して人手が不足している
経理業務は仕訳入力や決算処理、税務対応など専門性が高く、誰でもすぐに担当できるものではありません。そのため人手が慢性的に不足しがちです。
人が足りない状況で、一部の社員に業務が集中すると、その担当者がさらに多忙となり、業務の詳細が他の社員には見えない「ブラックボックス化」が進行します。結果的に、経理業務全体の属人化がより深刻になるのが大きな課題です。
ベテラン社員に知識が集中している
経理業務は長年の経験によって培われる部分が多く、自然とベテラン社員に知識やスキルが集まりやすい傾向があります。業務全体の流れや、例外処理への対応などは特に経験が物を言うため、ベテラン社員が担当する割合が高くなりがちです。
しかし、若手社員への教育体制が十分に整っていない場合、そのノウハウやコツが共有されず、知識の属人化が進行してしまいます。その結果、ベテランが不在の際に誰も対応できない状況が生まれ、業務リスクが高まるのが大きな問題です。
経理業務がマニュアル化されていない
経理業務がマニュアル化されていない場合、作業手順や処理方法が担当者の頭の中にだけ留まりがちです。
その結果、他の従業員に業務内容を共有したり、円滑に連携したりすることが難しくなり、属人化が進んでしまいます。急な担当者の不在や退職が発生すると、業務が止まるリスクも高まります。
マニュアルの整備は、属人化を防ぐための重要な一歩と言えるでしょう。
経理業務が属人化するリスク

経理業務が属人化すると、企業全体の経営リスクが高まります。具体的には以下のような問題が起こりやすくなります。
- 業務改善が行いにくい
- 不正が起こりやすい
- 業務が滞る可能性がある
- 品質低下につながりやすい
次項で、それぞれのリスクについて詳しく解説します。
業務改善が行いにくい
経理業務が属人化していると、作業の進め方や問題点が担当者の中に留まり、周囲からは見えづらくなります。そのため、どこに課題があるのかが把握しづらく、業務改善を進めることが難しくなります。
特に、担当者が独自の方法で処理を行っている場合、標準化や効率化の妨げとなり、結果的に業務の無駄が温存されてしまうリスクが高まります。経理体制を強化するには、属人化の解消が欠かせません。
不正が起こりやすい
経理業務が属人化すると、業務内容が外部から見えにくくなる「ブラックボックス化」が進み、不正の温床になりがちです。チェック体制が弱いままだと、不正な取引や架空経費の計上、資金の私的流用などに気付けない恐れもあります。
実際、多額の横領事件に発展するケースも珍しくありません。透明性を確保し、不正リスクを低減するには、属人化の解消と複数人によるチェック体制が不可欠です。
業務が滞る可能性がある
経理業務が属人化していると、担当者が急に休職や離職をした際に、大きな問題が発生します。理由は、他の従業員が業務の進捗状況や作業手順を詳しく把握しておらず、代わりに対応できないためです。
その結果、仕訳処理や請求書発行、支払い業務など、日常的な経理業務が滞り、企業活動全体に悪影響を及ぼしかねません。属人化を解消する取り組みは、経営の安定にも直結します。
品質低下につながりやすい
経理業務が属人化していると、他の従業員が業務の詳細を把握していないため、ミスが発生しても発見が遅れがちです。
ダブルチェックや業務の相互確認が行われない状態では、小さなミスが積み重なり、やがて経理データ全体の品質低下を招きます。
特に経理は金銭を扱うため、ひとつの重大なミスが資金繰りや経営判断に影響を与える恐れがあります。安定した経営のためにも、属人化の解消は急務です。
経理業務の属人化を解消するための5つの対策

経理業務の属人化を解消するには、計画的な対策が不可欠です。主な解決策は以下の5つです。
- 業務内容の洗い出し・ワークフローを改善する
- マニュアルを作成する
- ナレッジマネジメントを強化する
- 経理のアウトソーシングサービスを活用する
- クラウドサービスなどのシステムを導入する
次項では、それぞれの方法について詳しく解説します。
①業務内容の洗い出し・ワークフローを改善する
経理業務の属人化を解消するためには、まず現状の業務を詳細に洗い出すことが欠かせません。どの作業が誰の担当になっているか、どの工程が複雑化しているかを明確にし、業務の流れを見える化することが第一歩です。
現状分析を通じて、ワークフローのどこに無駄やボトルネックがあり、それが属人化を引き起こしているのか原因を特定することが重要です。問題が把握できれば、業務の分担方法や手順の標準化など、具体的な改善策を講じやすくなります。
②マニュアルを作成する
経理業務の属人化を防ぐには、業務の手順やポイントをまとめたマニュアルの作成が非常に効果的です。担当者しか知らない知識やノウハウを文書化することで、他の社員が業務を代行しやすくなり、業務の標準化が進みます。
また、法改正やシステム変更など、経理業務は頻繁にアップデートが必要なため、マニュアルは作成したままにせず、常に最新情報を反映させることが大切です。
担当者以外も変更点をすぐ把握できるよう、共有の仕組みを整えることで属人化の解消につながります。
③ナレッジマネジメントを強化する
ナレッジマネジメントとは、個人が持つ知識やノウハウを組織全体で共有し、有効活用するための取り組みです。経理業務で属人化を解消するには、このナレッジの共有を徹底し、知識を囲い込まない風土を作ることが不可欠です。
例えば、ベテラン社員が持つ「専門知識」や、業務を効率的に進める「コツ」を文章化したり、図やフローチャートにまとめて社内の共有フォルダに蓄積する方法があります。
こうした取り組みにより、誰が担当しても同じ品質で業務を遂行できる体制を整えることが可能です。
④経理のアウトソーシングサービスを活用する
アウトソーシングサービスとは、企業が自社の業務の一部を専門の外部業者に委託する仕組みを指します。経理のアウトソーシングを活用することで、業務が特定の社員に偏る属人化のリスクを大幅に軽減できます。
外部の専門家が業務を標準化された手順で遂行するため、特定の担当者がいなくても安定して経理業務が回る仕組みが整うのが大きな強みです。
また、最新の法改正や会計基準にも迅速に対応してくれるため、自社で人材育成や情報収集を行う負担も減らせます。
さらに、急な人員不足にも柔軟に対応できるため、経理体制を強化したい企業にとって非常に有効な選択肢です。
経理アウトソーシングとは?メリット・デメリットや料金、選び方など⑤クラウドサービスなどのシステムを導入する
経理業務の属人化を防ぐ手段として、クラウドサービスなどのシステム導入は非常に効果的です。
クラウドを活用すれば、データや進捗状況をリアルタイムで共有できるため、誰が、いつ、どの業務を行ったかが一目で分かり、ミスの早期発見やスムーズな引き継ぎが可能になります。
また、クラウド上の操作履歴が残ることで、内部統制の強化にもつながります。さらに、システム導入時には利用ルールを明確に設定し、手順を分かりやすくしておくことで、専門知識がない社員でも迷わず業務を進められる環境が整います。
業務の効率化と属人化の防止を同時に実現する、有効な解決策といえるでしょう。
経理業務の属人化を解消するメリット

経理業務の属人化を解消することは、企業に多くのメリットをもたらします。主な利点は以下の3つです。
- 業務の生産性が上がる
- 担当者不在時の業務継続が可能になる
- 担当者離職時の引き継ぎがスムーズになる
次項で、それぞれのメリットを詳しく解説します。
業務の生産性が上がる
経理業務の属人化を解消することで、特定の人に依存せず、複数の社員が同じ業務を担当できる体制が整います。その結果、作業が分散でき、忙しい時期でも業務が滞りにくくなり、生産性が大きく向上します。
また、業務フローや進め方を共有することで、ミスや課題を全員で把握でき、改善策を話し合いやすくなるため、業務効率のさらなる向上が期待できます。経理部門全体の底上げにつながる重要なメリットです。
担当者不在時の業務継続が可能になる
属人化を解消しておくことで、担当者が急な病気や家庭の事情で長期的に不在になった場合でも、他の社員が業務を引き継いで対応できます。
業務内容や手順が共有されていれば、滞りなく作業を進められるため、経理業務が止まるリスクを大きく減らすことが可能です。
担当者離職時の引き継ぎがスムーズになる
属人化を解消し、日頃から業務内容を他の社員と共有しておけば、担当者が退職する際も引き継ぎがスムーズに行えます。業務の流れやポイントが整理されているため、引き継ぎ漏れや混乱を防ぎ、経理体制の安定を保つことができます。
経理業務の属人化を解消したい場合はバックオフィスフォースにお任せください

経理業務の属人化は、業務停滞や不正リスク、引き継ぎの混乱など多くの問題を引き起こします。本記事では属人化が起こる理由やリスク、解消のための具体策をお伝えしました。
BackofficeForce株式会社では、プロマネ社員が実際の作業を行いながら業務マニュアルを作成・更新することで、業務の標準化と社内引き継ぎの負担軽減を実現します。
さらに、専用システムを活用し、業務を一元管理・可視化することでブラックボックス化を防ぎ、進捗状況を透明化。ミスや漏れを防ぎながら、安心して業務をお任せいただけます。
経理業務の属人化を解消し、持続的な業務運用を目指すなら、ぜひBackofficeForceにご相談ください。
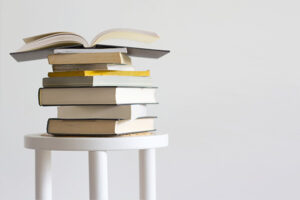
経理DX化の5つの課題とは?成功させるポイントを詳しく解説
2026-01-06 12:56
経理DX化とは、会計や経費精算などの経理業務をデジタル技術で効率化し、人的ミスや属人化を防ぐ取り組みのことです。しかし実際に進めようとすると、従業員の抵抗感やシステム選定の難しさ、取引先の非対応、法制度への理解不足など、思わ…

経理DX化の進め方を徹底解説!成功に導くための4つポイント
2025-12-23 11:47
経理DX化とは、経理業務をデジタル技術で効率化・自動化し、正確かつ迅速な意思決定を支援する取り組みです。紙や手作業中心の体制では、ミスや属人化、対応の遅れが生じやすく、経営スピードに追いつけません。特に近年は人手不足やリモー…

経理業務のDX化とは?必要性やメリット、進め方などの基本を解説
2025-12-16 11:23
近年、多くの企業で競合との差別化や生産性向上を目的に「DX化(デジタルトランスフォーメーション)」が注目されています。特に経理業務は、紙やExcel中心のアナログ運用が残りやすく、非効率や属人化が課題になりがちです。本記事で…

経理アウトソーシングはどこまで任せられる?依頼できる業務範囲
2025-12-09 15:34
経理業務の効率化を目的に「経理アウトソーシング」を導入する企業が急増しています。人手不足や担当者の属人化、急な退職などにより、経理体制の見直しを迫られる中堅企業は少なくありません。経理アウトソーシングとは、記帳や決算、給与計…

経理代行と記帳代行の違い|業務内容やメリット・デメリットを解説
2025-10-21 10:06
「経理代行」と「記帳代行」は一見すると同じような意味に見えますが、実際には役割や責任の範囲が大きく異なります。経理代行は記帳業務を含め、請求書発行や給与計算、決算対応まで幅広く担うのに対し、記帳代行は仕訳や帳簿作成に特化した…