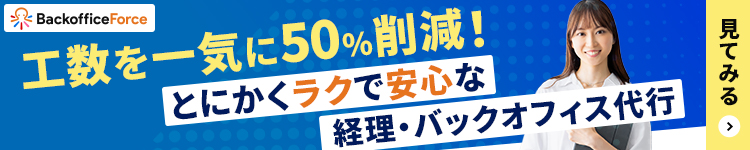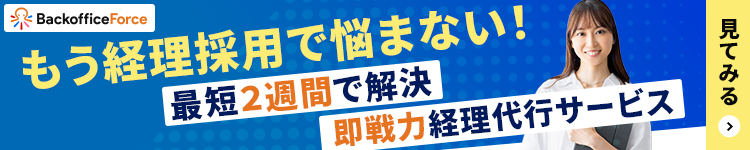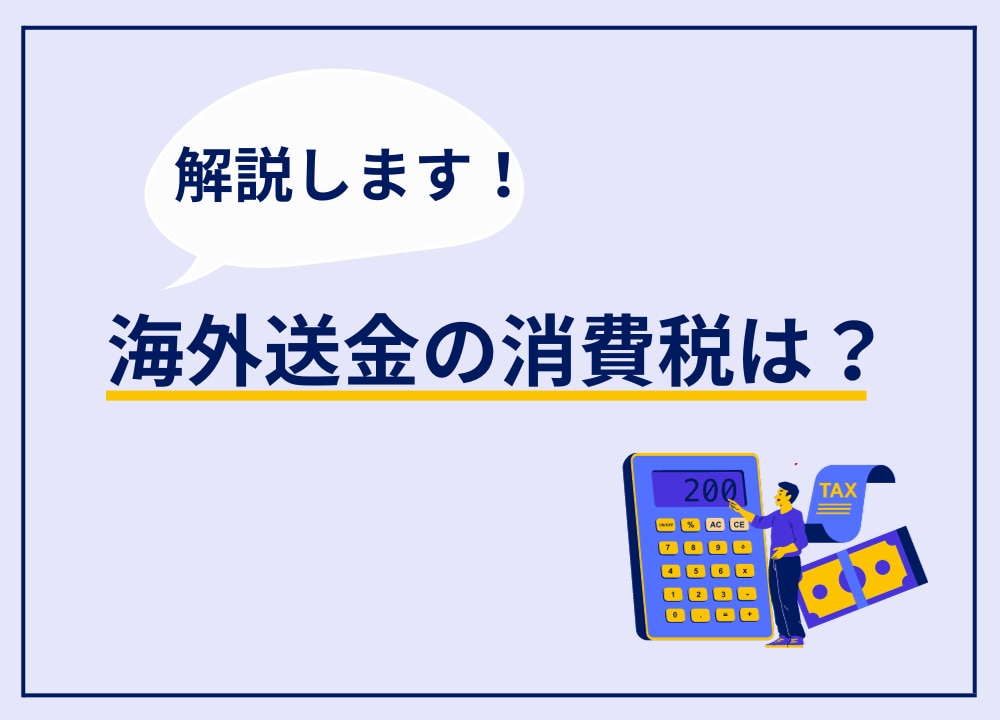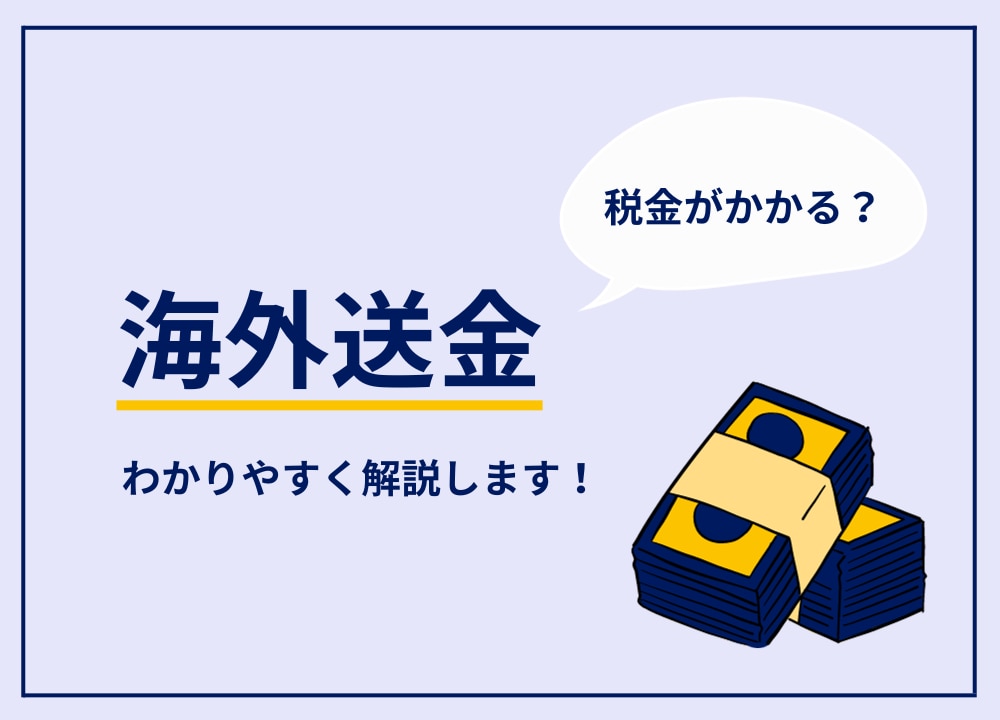経理マニュアルの作り方|作成のメリットやポイントなどわかりやすく解説

経理マニュアルとは、経理業務の流れや手順を標準化し、属人化やミスを防ぐための重要な指針です。各分野でマニュアル化が進む中、経理業務でもその動きは加速しています。
本記事では、経理マニュアルの作り方や作成時のポイント、マニュアル化によるメリットなどを詳しく解説します。経理体制の強化や効率化を目指す企業の皆さまは、ぜひ参考にしてください。
目次
経理マニュアルを作成する重要性
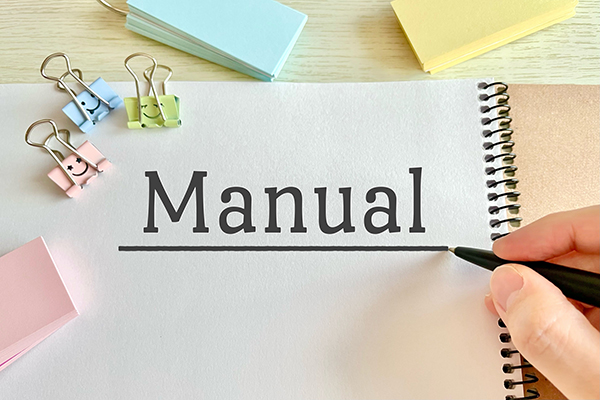
経理業務は企業運営において欠かせない重要な業務ですが、担当者ごとに手順や進め方が異なると、ミスが生じやすくなり、業務の質にばらつきが出てしまいます。
こうした属人化を防ぎ、経理の品質を安定させるためには、業務の流れを標準化することが必要です。
経理マニュアルを作成することで、誰が業務を担当しても同じ手順で作業が行え、一定の品質を保つことができます。
また、業務の可視化により改善点を見つけやすくなり、組織全体の効率化にもつながるため、経理部門にとって非常に重要な取り組みです。
経理マニュアルを作成するメリット

経理マニュアルを整備することで、業務の属人化防止や効率化、知識共有など多くの利点が得られます。具体的なメリットは以下の通りです。
- 経理業務の属人化を防ぐことができる
- 業務の効率化が期待できる
- 経理の専門知識や情報を共有できる
- ブラックボックス化の解決につながる
- 経理業務の引継ぎがスムーズになる
次項で、それぞれのメリットを詳しく解説します。
経理業務の属人化を防ぐことができる
経理業務は専門性が高く、担当者ごとにやり方が異なりやすいため、放置すると属人化が進みがちです。しかし、経理マニュアルを作成すれば、業務の流れや処理方法が明確になり、誰でも同じ手順で業務を行えるようになります。
属人化が解消されることで、特定の担当者に業務が集中して負担が過度に増えることを防げるほか、不正の温床となるブラックボックス化も避けられます。さらに、業務全体の見える化が進み、問題発見や改善もしやすくなるため、経理部門全体の安定運用に繋がります。
業務の効率化が期待できる
経理マニュアルが整備されていれば、手順やルールを都度教える必要がなくなり、説明にかかる時間や手間を大幅に削減できます。また、作業の進め方が統一されることでミスが起こりにくくなり、修正作業に費やす時間も減少します。
結果として業務全体がスムーズに進み、作業時間の短縮や生産性の向上が期待できます。経理部門の効率化を図るうえで、マニュアルは強力な武器となるでしょう。
経理の専門知識や情報を共有できる
経理マニュアルを作成することで、担当者が持つ専門知識やノウハウを全員で共有できるようになります。これにより、若手社員の教育がスムーズになり、業務の質を均一に保つことが可能です。
また、トラブルが発生した際にもマニュアルを参照することで迅速に対応でき、問題解決のスピードが上がります。経理部門全体のスキル底上げにも繋がる重要なツールです。
ブラックボックス化の解決につながる
経理業務は専門性が高く、数字の扱いも多いため、他部署からその実態が見えにくくなりがちです。この「ブラックボックス化」が進むと、業務の進捗や問題点が外から把握できず、経営上のリスクが高まります。
しかし、経理マニュアルを作成すれば、業務手順やルールが明文化され、どのような作業がどのように進んでいるかが一目で分かるようになります。
業務の見える化が進むことで、進捗管理や作業の確認がしやすくなり、万が一問題が発生しても早期発見や迅速な対応が可能になります。企業全体の透明性向上にも繋がる、大きなメリットです。
経理業務の引継ぎがスムーズになる
経理マニュアルが整備されていれば、担当者が急に退職や異動をする際も、業務の引継ぎが格段にスムーズになります。
マニュアルには業務の流れや重要なポイントが整理されているため、後任者は一から教わる必要がなく、自分で業務を理解しやすくなります。
その結果、引継ぎの時間や手間を大幅に削減でき、経理業務の停滞を防ぐことができます。企業にとって非常に心強い備えと言えるでしょう。
経理マニュアルの作り方

経理マニュアルを効果的に作成するには、計画性と具体性が欠かせません。以下のステップを押さえることで、実践的で役立つマニュアルを作ることができます。
- マニュアル化の目的を明確にする
- マニュアル作成のスケジュールを立てる
- 業務内容を洗い出す
- 作業ごとに担当者を設定する
- テンプレートを作成する
- テンプレートに従って本文を作成する
- 運用しながら定期的に改訂する
次項で、それぞれのステップについて詳しく解説します。
①マニュアル化の目的を明確にする
経理マニュアルを作成する際、最初に重要なのが「なぜ作るのか」という目的を明確にすることです。
例えば、属人化の解消、業務効率化、引き継ぎの円滑化など、組織が抱える課題に応じて目的を絞り込むことで、マニュアルの内容や構成の方向性がはっきりします。
さらに、この目的を関係者全員で共有することで、共通の目標に向かって協力しながら作業を進めやすくなります。目的がはっきりしていれば、完成するマニュアルの質も高まり、長期的に使える実践的なツールへと育てることができます。
②マニュアル作成のスケジュールを立てる
経理マニュアルの作成は、思った以上に時間がかかる作業です。最初に期限と各作業の段階ごとのスケジュールをしっかり決めておくことで、進捗管理がしやすくなり、効率的に作業を進められます。
具体的な日程が決まっていれば、作業の遅れを早期に察知し、軌道修正もしやすくなります。結果として、マニュアル作成が計画的に進み、完成度の高いものを期限内に仕上げることが可能になります。
③業務内容を洗い出す
経理マニュアルを作成するうえで、まず欠かせないのが業務内容の洗い出しです。どのような業務があり、誰が、いつ、どのように行っているのかを整理することで、経理業務全体の流れや全体像が明確になります。
全体像が把握できれば、漏れのない網羅的なマニュアル作成が可能になり、特定の業務が抜け落ちるリスクを減らせます。
また、この洗い出し作業の過程で、業務の重複や無駄が見つかることも少なくありません。結果的に、業務の効率化や見直しのきっかけにもつながるため、非常に価値のあるステップです。
④作業ごとに担当者を設定する
経理マニュアル作成では、作業ごとに担当者を設定することが重要です。それぞれの業務に詳しい担当者が執筆することで、内容の正確性や実務に即した質の高いマニュアルが作れます。
また、誰がどの部分を担当するかを明確にしておくことで、進捗状況の確認や修正の依頼もスムーズに行えます。結果として、作業全体の遅延防止や効率的なマニュアル作成につながります。
⑤テンプレートを作成する
経理マニュアルを分かりやすく、誰が見ても統一感のあるものにするためには、最初にテンプレートを作成することが大切です。フォーマットを揃えることで、情報が整理され、読み手が内容を探しやすくなります。
エクセルのシートや会計ソフトのフォームを活用するのも有効です。テンプレートには、最低限以下の項目を含めると良いでしょう。
- 管理コード
- 公開日
- 作成者
- 改訂日
- 業務の目的
- 業務の具体的な手順
- 改訂履歴と担当者
こうした情報をまとめることで、どの業務がいつ誰によって作成・更新されたかが一目で分かり、業務の透明性が向上します。
また、更新履歴を残すことで、変更内容の把握や過去データの参照もしやすくなり、長期的に運用できるマニュアルに仕上げられます。
⑥テンプレートに従って本文を作成する
テンプレートが完成したら、各項目に従って経理マニュアルの本文を記入していきます。それぞれの項目には、以下のような内容を記載すると効果的です。
管理コード
マニュアルを管理・検索しやすくするための識別番号。複数のマニュアルを体系的に整理する際に便利です。
公開日
マニュアルを社内で正式に公開した日付。運用開始時期を明確にするために記載します。
作成者
マニュアルを最初に作成した担当者の名前。責任の所在を明確にし、問い合わせ対応をスムーズにします。
改訂日
マニュアルを最後に更新した日付。最新版を把握しやすくし、古い情報の誤使用を防ぎます。
業務の目的
その業務が会社にとってどのような役割や必要性を持つのかを簡潔に記載します。
業務の具体的な手順
作業の流れを時系列で詳細に記載。誰が見ても同じ手順で業務を遂行できるようにします。
改訂履歴と担当者
改訂した日時や理由、改訂を行った担当者を記載。マニュアルの透明性や信頼性を高めます。
こうしたポイントをしっかり押さえて記載することで、実用的で活用しやすい経理マニュアルが完成します。
⑦運用しながら定期的に改訂する
経理マニュアルは、一度作成したら終わりというものではありません。制度改正や業務フローの変化、使用するシステムの入れ替えなど、経理業務の環境は常に変わり続けます。
そのため、運用を続ける中で生じた不備や手順の変更は、都度マニュアルに反映し、最新の状態を保つことが重要です。
また、実際に業務を行う現場からのフィードバックを積極的に取り入れ、わかりにくい部分や改善すべき箇所を修正していくことが、マニュアルを使いやすくし、業務品質の向上につながります。継続的な改訂こそが、経理マニュアルを「生きた」ツールにする鍵です。
経理マニュアルの作成における3つのポイント

経理マニュアルは単に作業手順を並べるだけではなく、誰もが使いやすく、汎用性の高い内容に仕上げることが重要です。特に以下のポイントを意識することで、実用的で現場で役立つマニュアルが作れます。
- 図やフローチャートで記入する
- 専門用語や略語は控える
- ミスやトラブル時の対応方法も記載する
- クラウドサービスやITツールを活用する
次項では、それぞれのポイントを詳しく解説します。
図やフローチャートで記入する
経理マニュアルでは、複雑な業務の流れを文章だけで説明しようとすると、読み手が内容を理解しにくく、混乱を招くことがあります。
特に、複数の関係者が関わる業務や、段階を踏んで進行する業務では、図やフローチャートを活用することが効果的です。
例えば、請求書発行から承認、支払いまでの流れや、決算作業のスケジュールなどは、図解にすることで全体のつながりが一目で把握できます。
視覚的に情報を整理することで、誰が見ても業務の流れが理解しやすくなり、業務ミスの防止にもつながります。図やフロー図は、わかりやすいマニュアル作りの強い味方です。
専門用語や略語は控える
経理マニュアルに専門用語や略語が多用されていると、読み手が内容を正しく理解できず、誤解やミスの原因になりかねません。特に経理の経験が浅い人にとっては、難解な用語がハードルとなり、読む意欲を削いでしまうこともあります。
専門用語はできるだけ平易な言葉に置き換え、誰が読んでも理解できる内容にすることが大切です。やむを得ず使う場合は、簡単な説明を添えると親切です。
ミスやトラブル時の対応方法も記載する
経理マニュアルには、平常時の手順だけでなく、ミスやトラブルが発生した際の対応方法も必ず盛り込むべきです。
たとえば「仕訳を誤って登録した場合は、〇〇画面で修正する」「請求書を誤送付した際は、直ちに取引先へ連絡し、再発行する」など、具体的な対応例を記載しておくことで、現場での混乱を最小限に抑えられます。
担当者が一人で悩まず、すぐ行動に移せる指針となるため、業務の安定性が増します。結果的に、企業全体のリスク管理体制の強化にもつながり、トラブル発生時の迅速な対応が可能になります。
クラウドサービスやITツールを活用する
経理マニュアルを紙やローカル保存だけで管理していると、更新のたびに再配布が必要で手間がかかり、最新情報の共有が遅れがちです。そこで有効なのがクラウドサービスの活用です。
クラウド上にマニュアルを作成・保管しておけば、インターネット環境さえあればオフィス外からでもリアルタイムで閲覧・編集が可能になり、テレワークや複数拠点での利用にも対応できます。
また、ITツールを併用することで、マニュアル改訂のスケジュール管理や更新履歴の記録が簡単になり、納期遅延や更新漏れのリスクも減少します。
さらに、一度内容を修正すれば再配布の手間が不要になり、全社員が常に最新情報を共有できる点も大きなメリットです。こうしたツール活用は、経理業務の効率化と属人化防止の強い味方です。
経理マニュアルの作成依頼はBackofficeForceへご相談ください

経理マニュアルの作成は、業務の標準化や属人化防止、引き継ぎの円滑化に不可欠です。しかし、経理の専門知識や現場の状況を理解しながら、分かりやすく実用的なマニュアルを整備するのは容易ではありません。
BackofficeForce株式会社では、プロマネ社員が実際に作業を行いながらマニュアルを作成・更新し、引き継ぎ負担を減らす体制を構築します。
また、専用システムを活用した業務の一元管理と可視化により、ブラックボックス化を防ぎ、タスクの進捗やナレッジの蓄積を徹底。
さらに月次レポートによる改善提案など、単なる作成に留まらず業務効率化までトータルに支援します。
「業務が属人化していて不安」「どこから手を付けたらいいか分からない」というお悩みをお持ちの方は、まずは無料オンライン相談をご活用ください。BackofficeForceが、貴社に最適な経理体制づくりを全力でサポートいたします。

経理業務を効率化する7つの方法|メリットや手順をわかりやすく解説
2026-01-21 15:18
経理業務の効率化は、「どれだけ日々のルーティンをムダなく正確に回せるか」で成果が大きく変わります。経理は定型化できる業務が多く、手順の見直しやツール活用次第で、作業時間・ミス・ストレスをまとめて削減できます。本記事では、経理…

経理代行サービスの失敗しない選び方6選|メリットや流れも解説
2026-01-14 09:41
経理代行とは、企業の経理業務を専門家に委託するサービスです。仕訳や請求書処理、月次決算などを外部に任せることで、担当者の負担を軽減し、経営層が本業に集中できる環境を整える企業が増えています。近年は人手不足や属人化、急な退職と…
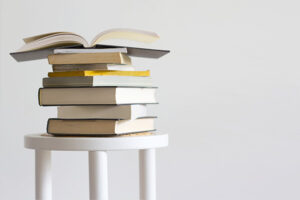
経理DX化の5つの課題とは?成功させるポイントを詳しく解説
2026-01-06 12:56
経理DX化とは、会計や経費精算などの経理業務をデジタル技術で効率化し、人的ミスや属人化を防ぐ取り組みのことです。しかし実際に進めようとすると、従業員の抵抗感やシステム選定の難しさ、取引先の非対応、法制度への理解不足など、思わ…

経理DX化の進め方を徹底解説!成功に導くための4つポイント
2025-12-23 11:47
経理DX化とは、経理業務をデジタル技術で効率化・自動化し、正確かつ迅速な意思決定を支援する取り組みです。紙や手作業中心の体制では、ミスや属人化、対応の遅れが生じやすく、経営スピードに追いつけません。特に近年は人手不足やリモー…

経理業務のDX化とは?必要性やメリット、進め方などの基本を解説
2025-12-16 11:23
近年、多くの企業で競合との差別化や生産性向上を目的に「DX化(デジタルトランスフォーメーション)」が注目されています。特に経理業務は、紙やExcel中心のアナログ運用が残りやすく、非効率や属人化が課題になりがちです。本記事で…