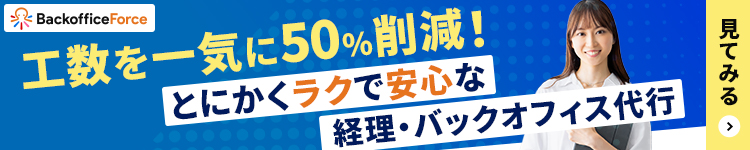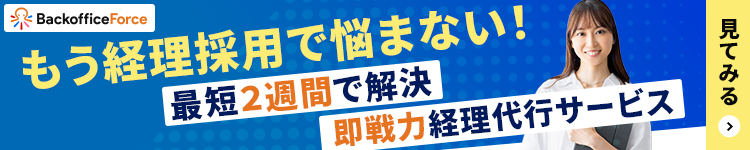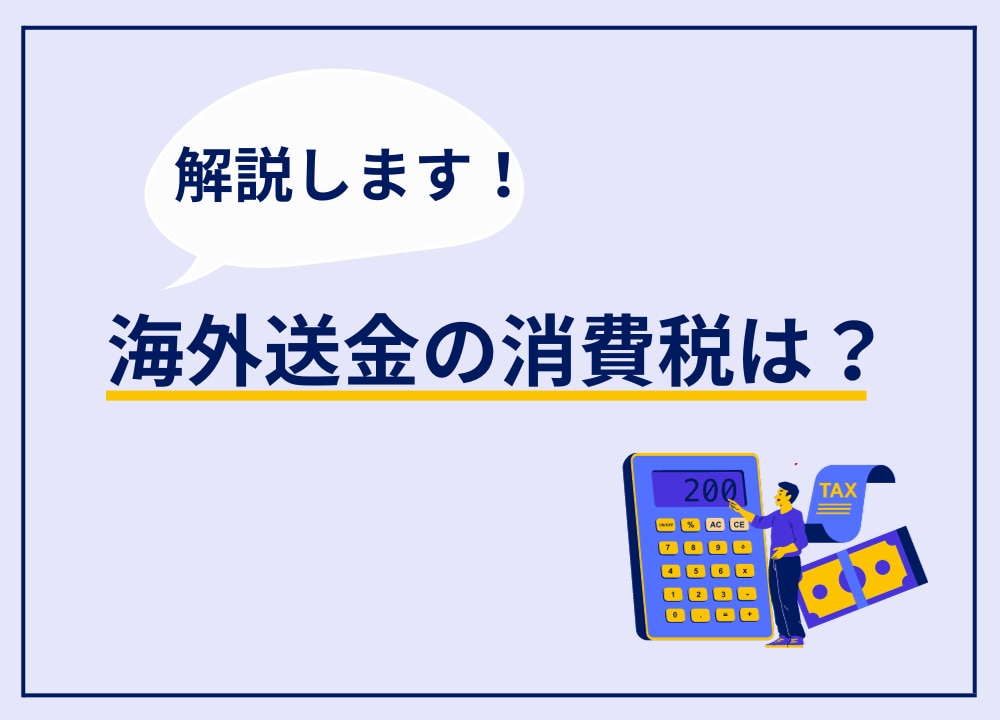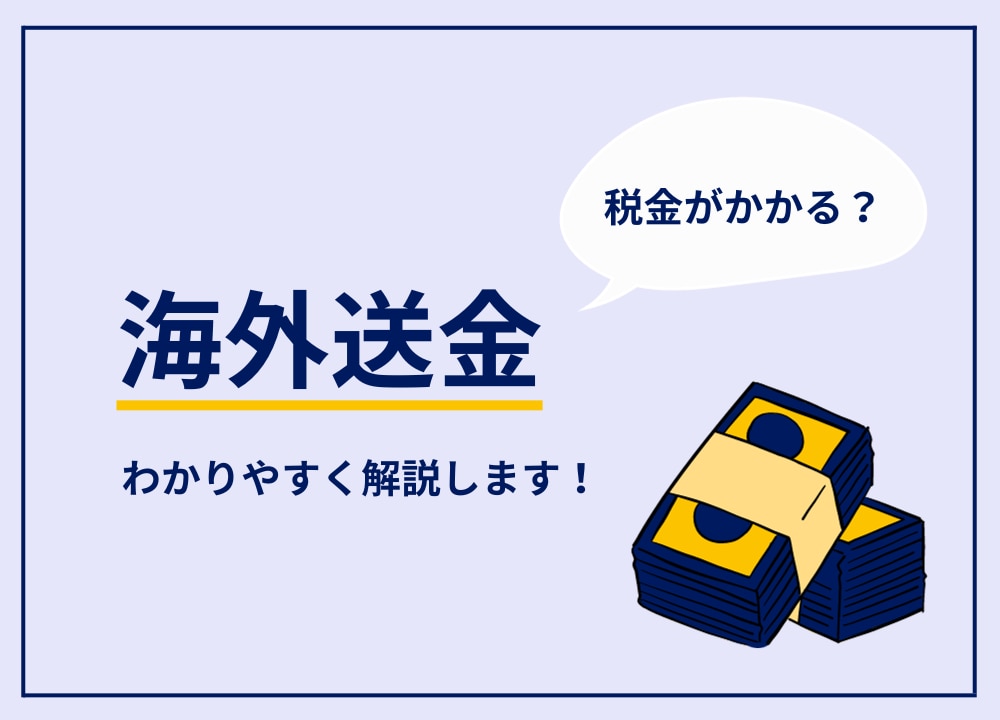バックオフィス代行とは?依頼できる業務やメリット、費用相場など

経理・総務・人事といった事務作業を外部に任せる「バックオフィス代行サービス」は、業務の効率化や人材不足の解消を目的に多くの企業が導入を進めています。限られたリソースをコア業務に集中させたい中堅企業にとって、有力な選択肢のひとつです。
本記事では、バックオフィス代行で依頼できる具体的な業務内容や、導入によるメリット・デメリット、費用の目安、サービス選定のポイントまでを詳しく解説します。
目次
バックオフィス代行サービスとは

バックオフィス代行サービスとは、経理・人事・総務などの事務業務を専門業者に外部委託する仕組みです。これらの業務はルーティン化しやすく、マニュアルによる標準化も可能なため、外注化しやすいのが特徴です。
自社で人手を確保しにくい場合や、業務負担の軽減を図りたい企業にとって、効率的な選択肢となります。近年では、業務改善やDX推進の一環として導入する企業も増えています。
バックオフィス代行サービスの種類

バックオフィス代行サービスには、提供形態や人材のスキルによって複数の種類があります。
リモート対応中心の「オンライン型」、常駐スタッフが業務を行う「オフライン型」、経理や労務などに特化した「専門特化型」、幅広い業務を支援する「アシスタント型」などが代表例です。
自社の課題や目的に応じて、最適な形態を選ぶことが成功のカギとなります。
| 種類 | 特徴・違い | メリット | デメリット | 適している業務 |
|---|---|---|---|---|
| オンライン | リモートで業務を代行 | コストを抑えやすい/全国どこでも対応可能 | 対面でのやりとりができず、緊急対応に時間がかかる | 経理入力、勤怠集計、請求書発行など |
| オフライン | 担当者が訪問・常駐して業務を実施 | 密な連携が可能/柔軟な対応力がある | コストが高め/場所に制限がある | 書類管理、郵送業務、庶務全般など |
| 専門特化型 | 経理・人事・法務など専門分野に特化 | 高度な知識が必要な業務も安心して任せられる | 業務範囲が限定的/料金が高め | 決算業務、社会保険手続き、契約管理など |
| アシスタント型 | 幅広い業務を柔軟に対応するマルチ人材 | 業務全体を横断して支援/小規模業務にも対応可能 | 専門性がやや劣る場合がある/業務の切り分けが必要 | スケジュール管理、資料作成、庶務対応など |
バックオフィス代行に依頼できる業務内容

バックオフィス代行サービスでは、経理や人事、総務、営業事務など、企業の間接業務を幅広く外部に委託できます。これにより、業務の効率化やコア業務への集中が可能になります。
ただし、代行会社によって対応範囲や専門性には差があるため、自社のニーズに合った業務に対応しているかどうかを事前に確認することが重要です。次項では、具体的に依頼できる業務内容を分野ごとに解説していきます。
経理
経理業務におけるバックオフィス代行では、
- 記帳処理
- 経費精算
- 月次・年次決算業務
- 請求書の発行・管理
など煩雑で手間のかかる業務を一括して依頼できます。とくに専門知識を要する決算業務などは、経験豊富な外部スタッフに任せることで、ミスの防止や業務品質の向上が期待できます。
また、社内に経理担当者を常駐させる必要がなくなり、採用・教育コストの削減にもつながります。継続的な業務改善支援を受けられるのも利点です。
経理代行とは?サービス内容・メリット・選び方のポイントなど解説総務
総務分野でバックオフィス代行に依頼できる業務には、
- 資料作成や備品管理
- データ入力
- 各種リサーチ業務
などがあります。こうした雑務や定型作業を外部に任せることで、社内リソースを戦略立案や経営判断といったコア業務に集中させることが可能です。
総務の負担軽減は、部門全体の生産性向上や経営のスピードアップにもつながり、間接的に企業全体の競争力強化にも寄与します。
人事・労務
人事・労務分野でバックオフィス代行に依頼できる業務には、
- 給与計算
- 勤怠管理
- 社会保険関連の手続き
- 採用に関する事務手続き
などがあります。これらの業務は定型かつ手続きが煩雑なため、外部に任せることで社内の作業負担を大幅に軽減できます。
結果として、採用戦略の立案や人材育成など、より重要度の高い業務に集中できる環境が整い、人事部門全体の機能強化にもつながります。
営業事務
営業事務においてバックオフィス代行に依頼できる業務には、
- 顧客データの管理
- 見積書や契約書の作成
- 受注処理
- 在庫管理
などがあります。これらは煩雑かつ定型的な作業が多く、営業担当者が対応すると本来の業務に集中できません。
代行サービスを活用すれば、アポイント獲得や商談、クロージングといったコア業務に専念でき、分業体制による生産性向上とスピード感ある営業体制の構築が可能になります。
バックオフィス代行を利用するメリット

バックオフィス代行を活用することで、企業は業務効率化を実現し、組織全体の生産性を高めることができます。さらに、人件費や固定費の見直しにつながり、コスト削減や属人化の解消といった副次的な効果も期待できます。
- 業務効率化により生産性が向上する
- コスト削減ができる
- 属人化が解消できる
業務効率化により生産性が向上する
バックオフィス代行を導入すれば、請求書処理や勤怠管理、データ入力などのノンコア業務を外部に任せることができ、従業員が本来注力すべきコア業務に専念できます。
例えば、営業部門であれば、顧客対応や商談に集中できるようになり、売上アップや新規顧客獲得といった成果につながる可能性が高まります。また、ルーティン業務の負担が軽減されることで、業務全体のスピードと質も向上し、組織全体の生産性向上に寄与します。
コスト削減ができる
バックオフィス代行を活用すれば、自社で社員を採用・育成するよりも人件費を抑えられる可能性があります。求人広告や面接、入社後の教育といった採用にかかるコストや工数も不要です。
必要なときに必要な分だけ依頼できるため、業務量に応じた柔軟なコスト設計が可能になり、固定費を変動費に置き換えることができます。
また、業務効率が向上することで残業時間の削減にもつながり、間接的なコストダウンにも貢献します。導入次第では、経費全体の見直しにもつながる有効な手段です。
属人化が解消できる
バックオフィス業務は長年同じ担当者が対応していることが多く、自然と業務が属人化しがちです。属人化が進むと、担当者が休職・退職した際に業務が停滞するだけでなく、引継ぎの負担やミスのリスクも高まります。
さらに、業務改善が進みにくくなり、企業全体の成長を妨げる原因にもなります。バックオフィス代行を導入すれば、業務が標準化され、誰でも対応可能な状態に整えられるため、属人化の解消と業務の継続性確保に大きく寄与します。
バックオフィス代行を利用するデメリット

- ノウハウが社内に蓄積されにくい
- 情報漏洩のリスクがある
- 緊急時の対応が遅れるリスクがある
バックオフィス代行には多くの利点がありますが、すべてを委託することで社内にノウハウが残らなかったり、情報管理の難しさからトラブルにつながる場合もあります。次項で注意点を詳しく解説します。
ノウハウが社内に蓄積されにくい
バックオフィス代行を長期間活用していると、業務の進め方やノウハウが社内に蓄積されにくくなる恐れがあります。その結果、急遽内製化が必要になった際に、対応できない事態も想定されます。
こうしたリスクを避けるためにも、業務マニュアルの作成や手順の見える化を代行先に依頼し、社内共有できる体制を整えておくことが重要です。
情報漏洩のリスクがある
バックオフィス代行では、給与データや顧客情報などの機密情報を外部に預けるため、情報漏洩や不正アクセスといったリスクが伴います。
こうしたリスクを最小限に抑えるためには、代行会社のセキュリティ対策や運用体制、個人情報の取り扱いルールを事前にしっかり確認しておくことが不可欠です。秘密保持契約(NDA)の締結も検討しましょう。
緊急時の対応が遅れるリスクがある
バックオフィス代行では、連絡手段がメールやチャット中心になることが多く、緊急時の対応が遅れるリスクがあります。特にトラブル対応や期限が迫った業務では、タイムロスが大きな影響を及ぼす可能性も。
こうした事態を防ぐためには、緊急連絡時のルールや対応フロー、連絡先などを事前に明確に決めておくことが重要です。
バックオフィス代行の料金形態と費用相場
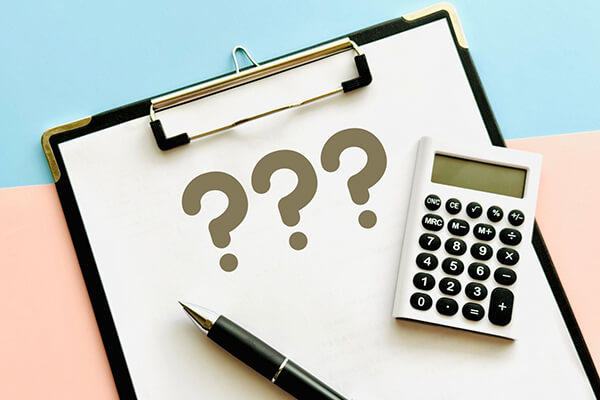
バックオフィス代行の料金形態は、依頼内容や業務量に応じて複数のタイプがあります。以下に主な形態と費用相場をまとめます。
- 月額固定料金型:業務量にかかわらず、月額10万~50万円程度。予算が立てやすいのが特徴。
- 時間単位料金型:作業時間に応じた料金で、時給3,000円~8,000円程度。スポット的な依頼に最適。
- 作業量ベース型:処理件数に応じて費用が決まり、1件あたり500円~5,000円程度。明確な作業単位がある業務に向いています。
- カスタマイズ型:業務範囲や体制に応じて柔軟に対応し、月額20万~100万円以上のケースも。中~大規模企業向け。
目的や予算、求めるサポート体制に応じて、最適な料金形態を選定しましょう。
バックオフィス代行サービスを選ぶ5つのポイント

バックオフィス代行を成功させるには、自社に合ったサービスを選ぶことが重要です。以下に挙げる5つのポイントを押さえることで、失敗のリスクを減らし、安心して業務を任せることができます。
①委託したい業務を全て対応できるか
代行会社によっては、依頼したいすべての業務に対応できない場合があります。業務範囲が限定されていると、かえって社内に追加の負担が発生し、二度手間になる恐れもあります。また、繁忙期や急な依頼にも対応できる体制かどうかも重要です。
業務の内容だけでなく、ボリュームや対応スピード、柔軟性についても事前に確認し、自社の要件を満たすか慎重に見極めましょう。
②依頼する業務の専門知識が豊富か
バックオフィス代行会社には、それぞれ得意とする分野があります。例えば、経理に強い会社もあれば、人事・労務に特化している会社もあります。
自社が依頼したい業務に対して、十分な専門知識と対応実績を持っているかを確認することが重要です。複数の会社に話を聞き、提案内容や担当者の知識レベルを比較することで、ミスマッチのないパートナー選びが可能になります。
③実績や成功事例が豊富か
バックオフィス代行を依頼する際は、これまでの実績や成功事例が豊富な会社を選ぶことが重要です。実績が少ない会社では、対応力や柔軟性に不安が残り、期待通りの成果が得られない可能性もあります。
公式サイトに掲載されている事例や導入企業の声、口コミなどを確認し、自社の業種・規模に近い対応経験があるかを見極めましょう。信頼できる事例は安心して任せられる判断材料になります。
④セキュリティ体制が整っているか
バックオフィス代行では、機密情報や個人情報を扱うため、セキュリティ体制の確認は不可欠です。万が一、情報漏洩が発生すれば、企業の信頼失墜や損害賠償など、重大なリスクにつながります。
事前に「プライバシーマーク」や「ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)」の取得有無を確認しましょう。また、アクセス権限の管理方法や従業員への教育体制などもあわせてチェックすることが大切です。
⑤費用設定が適切か
費用が見合っていないと、バックオフィス代行の導入そのものが無駄になってしまう可能性があります。高額すぎれば自社採用の方が安く済むこともあり、安すぎれば質に不安が残ります。
まずは業務内容に応じた予算を設定し、複数社から見積りを取って費用感を比較しましょう。料金体系(固定・従量・カスタマイズなど)も確認し、必要なサービスが含まれているかを見極めることが重要です。
バックオフィスの業務委託をご検討中ならBackofficeForceにお任せください!

バックオフィス代行は、業務の効率化や人手不足の解消、コスト削減、属人化の解消など多くのメリットがある一方で、依頼先選びや情報管理には注意が必要です。
本記事では、代行可能な業務の種類やメリット・デメリット、費用相場、会社選びのポイントまでを詳しく解説しました。
バックオフィスの業務委託をご検討中なら、ぜひBackofficeForceにご相談ください。経理・総務・人事・労務など、専門性の高い業務を即戦力人材が対応。マニュアル整備や専用システムによるタスク可視化により、業務の属人化やミスを防止し、安定的な業務運用を実現します。
柔軟な支援体制と豊富な実績で、貴社の課題に寄り添い、最適な業務プロセスをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

バックオフィスBPOとは?メリットや活用する流れ、選び方などを解説
2025-12-02 11:46
バックオフィス業務は経理・人事・総務など範囲が広く、担当者に求められるスキルも多岐にわたります。そのため、中堅規模の企業では人材不足や属人化、業務停滞といった課題を抱えることが少なくありません。こうした悩みに有効なのが「バッ…
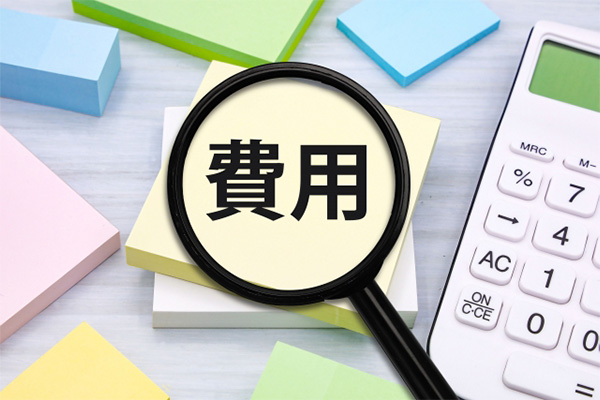
バックオフィス代行の費用相場はいくら?費用対効果の高め方も紹介
2025-11-25 13:10
バックオフィス代行とは、経理・財務・労務・総務などの事務業務を専門の外部パートナーに委託するサービスです。代行会社ごとに料金体系や提供範囲は大きく異なるため、費用相場を正しく把握し、自社に合った活用方法を選ぶことが重要です。…

バックオフィス業務は丸投げできる?メリットや注意点を詳しく解説
2025-11-19 11:29
バックオフィス業務は丸投げできる?バックオフィスの「丸投げ」とは、企業の経理・人事・総務・法務といった間接部門の業務を、外部の代行会社にすべて一任することを指します。従来は一部業務だけをアウトソーシングするケースが多く見られ…

バックオフィスの業務一覧|よくある課題や改善方法を解説
2025-10-24 16:08
企業の成長を支えるうえで欠かせないのが、バックオフィス業務の安定運営です。経理や人事、総務、労務など幅広い領域を網羅するこれらの業務は、一つでも滞ると経営全体に影響を及ぼします。そのため、効率化や体制強化が企業の競争力向上に…

バックオフィス代行とは?依頼できる業務やメリット、費用相場など
2025-10-01 16:29
経理・総務・人事といった事務作業を外部に任せる「バックオフィス代行サービス」は、業務の効率化や人材不足の解消を目的に多くの企業が導入を進めています。限られたリソースをコア業務に集中させたい中堅企業にとって、有力な選択肢のひと…